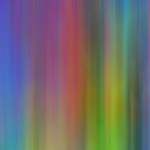━━━慟哭。
奏汰は、幼馴染の亡骸のすぐそばで、膝をつき、悲しみに涙を流し、声を張り上げて泣いている。
「うぅ………あぁッ!……ああッ!」
胸が、心臓が切り裂かれるように痛い。心が痛い。苦しい。まるで自分も彼女の後を追ってしんでしまいそうだ。
ずっと伝えたかった想いを、彼女に伝えた。
いつも聞きたかった言葉を、彼女から聞いた。
それなのに、奏汰の心は満たされない。行き場なのない悲しみで押しつぶされそうなのである。
彼にとって、今この時の心境は、世界中の誰にも、学校の先生にも、両親にも、友達でさえ代弁することの出来ない。
中学生から高校生になったばかりの、幼さの残る少年は、人生で何度か訪れる困難の壁にぶつかっているのだ。
小黒友里は死んだ。彼の目の前で。
彼にとって彼女の存在は大きかった。
それは彼自身が思っている以上であった。
隣同士としての友里。友達としての友里。幼馴染としての友里。そして、愛する人としての友里。
もう二度と、目を覚まして、彼にあれこれ実験を手伝わせたり、発明品を見せたり、それから、2人で笑う事ももう二度とないのだ。
奏汰は顔を伏せる。
涙が頬を伝い、奏汰の手の甲に落ちる。
ようやく声を抑え、涙が頬を伝う感覚に気づくころには、辺りからサイレンの音が近づいて来ていた。
消防車、救急車、パトカーのサイレン。
赤色灯が暗い夜道に、ちらちらと光っている。
妨害電波によって通報が思うようにいかない。しかしながら、先程の非常ベルや、フライア主砲による爆発は、近隣住民の意識を引き、警察や消防に連絡し、彼らが駆けつけてきたとしても不思議ではない。
緊急を知らせるためのはずのサイレンは、この別れの義を終わらせる合図となった。
奏汰には、彼女との別れにゆっくりと時間を使うことさえ許されていなかったのだ。
奏汰は、警察官にこちらの居場所を伝えようと立ち上がった。振り向くと、彼の視界の端に見えた大きな影が入った。
友里が死んだときも、奏汰が悲しみに打ちひしがれているときも、ずっと2人を見守っていたそれ。
フライアだ。
そこで彼の頭にある言葉がよぎった。
彼女が死ぬ間際に言った言葉。
【この子を、お願い…………。きっと、奏汰の力になってくれる…………。大切にして、あげて………】
この子とはつまり、今2人を静かに見つめているこの金属のロボット、フライアのことであろう。
友里は奏汰に「フライアをよろしく頼む」と遺言を残したことになる。
彼女は一体、ただの高校生の男子に何を見出したのだろうか。このトンデモ兵器をどう扱えというのだろうか。
奏汰は1から10まで教えてもらう必要があったし、友里の方も丁寧に自分の願いを、同じように1から10までを伝えたかっただろう。
しかし、過ぎてしまった時間は取り戻せない。
失った命ももう戻ろらない。
彼は進むしかないのだ。
フライアを託された以上、無碍にこの戦闘ロボットを放り出して自分だけ逃げるようなことは出来ない。
奏汰は考えた。もしこのままフライアの存在に気づかれれば、まず間違いなく没収されるだろう。
これだけの破壊力を持った危険なロボットを疎ましく重い、解体されるかもしれない。
であれば、駆けつけてきてくれた警察官、救急隊、消防士に見つからないようにしなけらばならないのは明白だった。
奏汰は周辺の状況を確認する。
坂を上った少し離れたところで、人が数人うろうろと動いているのが、暗いながらも薄っすら分かった。
もう車から降りて、対応に当たろうとしているのだろう。
もうすぐ、彼らはここにくる。そうすれば友里の亡骸とそばにいる奏汰と巨大なロボットを発見するだろう。今すぐにここを立ち去らなければならないが、友里を連れて行くか迷った。結局は、彼女の亡骸を抱えていたところで、無力な自分にはどうすることも出来ない、と奏汰は考え、彼女をそのまま大地に眠りにつかせることにした。
「友里…………」
友里に背を向けて立ち上がり、奏汰は友里から受け取ったペンダントをぎゅっと握った。
彼女の想いを今確かに受け取ったと、噛みしめるように。
それから、友里と同じようにペンダントを首にかけた。
彼女はフライアに何か指示を下す際、このペンダントを握っていた。
「フライア」と声をかけてみる。
それに反応してフライア上半身をやや前に傾け、カメラアイが奏汰の身体を見据えた。
「俺を乗せて、安全そうな場所に隠れろ」
フライアは命令を実行するため、手を地面すれすれまで近づけて、奏汰の足の踏み台にした。
彼がその手に乗るのを確認するとフライアは抱え、脚部のキャタピラを回転させてその場を後にした。
地面を削りながら車ほどの速さで走るフライアの腕に抱きかかえられた奏汰は振り向いて、地面に横たわる友里を見つめる。
さようなら、友里。と心で呟きながら。
迫りくる風で涙が宙に舞う。
こんなにも悲しい夜に、月は無情にも美しく光り輝いている。
まるで、ちっぽけな人間に対して絶大な力を振るう夜の女王のように。
それか、もしくは、友里の魂を天へと誘うための道しるべを示している、親切な道案内人と考えることも出来るかもしれない。
それほどまでに、この真ん丸の月は見る人を魅了してしまうものであった。
明るく光りすぎて、空がうっすらと青い。
そんな空の事情など露ほども知らぬ警察官らしき人影が、ライトを持って友里に近づいていった。
少女の遺体を発見したのか、彼らは大慌てで無線に連絡している。
それを見届け、奏汰はペンダントを握り、フライアに県境にある森に向うように命じた。
興味のあるような人や特別な用のある人以外はあまり近づかないような森なら何とか、フライアを隠せるだろうと考えたのだ。
彼の指示の通りに、フライアはキャタピラに動力を伝え、坂を下り、24時間営業のコンビニエンスストアがある角を曲がり、個人が管理している畑を通り過ぎ、用水路にかかる橋を渡った。
友里から離れる際に左側に浮かんでいたはずの月は、すでに真後ろに位置していた。
出来るだけ車通り人通りを避けたつもりではあったが、森へ行くにはどうしても大通りを渡らなければならなかった。
人の気はそこまで多くはなかったが、公園に1人佇む時計が9時を指す頃、まだ帰宅途中の通行人には目撃されてしまった。
フレイアを見たその数人の通行人も、自分の目を疑い、固まってしまい、声が出せなくなっていた。
通行人たちの中には、きっと幻でも見たのだろうと思い、首を傾げる者もいたし、先日工場を破壊したロボットなのではないかと血の気を引く者もいた。
とにかく、フレイアは森の近くへ何とか辿り着いた。
森へ入って行くための道の入り口には、黄色と黒の棒がかけられた2つの三角コーンが置かれており、立ち入り禁止という札が中央に吊り下げられていた。
「進んで」
ペンダントをぎゅっと奏汰が握ると、フライアはそのまま中へと入って行った。
足場は先に進むほど悪くなっており、最初は砂利ばかりで、普通車でもなんとか通れるような道であったが、奥はもはや道と呼ぶには抵抗があるほど凸凹としていて、恐らくはオフロード車のような不整地に耐性のある車でなければ通れないような険しいものであった。
そんな場所もお構いなしにフライアは、奏汰を抱き抱えたままどんどん進んでいく。
上下左右に奏汰の身体が揺さぶられてはいるが、今のところ危険はない。
それどころか、平坦な地よりもこうした道の方が本領発揮出来ると示すように、意気揚々と山を駆け抜ける。
フライアの足回りはかなり頑丈でありながら柔軟性も兼ね備えた造りとなっているようで、キャタピラでも進むのに苦労するような箇所では人間と同じように器用に歩いた。
倒木で道が塞がれてしまっていた時には、機体の重量など無関係であるかのように、俊敏な動きで飛び越えた。
もうすっかり街灯がなくなると、辺りは木々の影しか見えず、あとは月の光が唯一の照明になるのである。
その光も、木々の影に阻まれては活躍の場はない。
真っ黒な木々の影は、風で不気味に揺れており、1人でここに来てしまったことに若干の後悔の念があったが、フライアのこともありそのまま奥へと進行するほかなかった。
それでも若干の恐怖は持ち合わせており、また、視界が役に立たない今、奏汰はやむを得ず目を閉じ、とにかく耳を澄ませた。
虫が鳴いている。
何の虫かは定かではないが、ジーッ、ジーッ、と夏が近づいてきたことを知らせる声を仲間と共に森中に響かせていた。
その中に紛れる、ウィーン、ウィーン、ガシャン、ガシャンというフライアが発する機械音や足音。
数分ほど立つと、やがて、それらの音に加えて水が流れる音が徐々に聞こえてきた。
滝のように大量に水が流れ落ちるような音でも、雨のように地面を叩くような音でもなく、ただ優し気に流れる清流の音のようであった。
それは段々と大きくなっていく。
目を開け、右側に瞬くなにかが見えた。
それが気になり、奏汰はペンダントを握った。
「右側に行ってくれ」
すぐさまフライアは進路を変え、右側に進むと、茂みを踏み越えて森を出た。
そこには、広くそして浅い河が流れていて、奏汰たちが位置しているのは丁度S字にカーブしているところの出っ張りの部分であった。
「そうか、ここ河になっていたのか……………」
奏汰は辺りを見回した。
この辺までくれば、見つからないだろう。
奏汰は再び考えた。
車で行けば、そんなに遠くないとはいえ、歩いて帰ることは困難だ。
それに、敵の部隊に見つかる可能性だってある。
それならこの森の中で、フライアと居た方が賢明だ。
奏汰はそう結論づけるとため息を漏らし、ペンダントをぎゅっと握った。
「俺をコックピットに入れてくれ」
返事をする代わりに、ペンダントが青く光り、フライアは自身の手を胸元のコックピットに近づけた。
ハッチは自動で水平に開いた。
先ほど、友里が座っていた席。
そこに今度は奏汰が座る。
シートにあった彼女の温もりはすでになくなっており、すっかり冷えていた。
奏汰はシートに座ると、目の前にあるモニターに両腕を重ね、その上に顔を埋め、夜が明けるのを待つことにした。
どっと疲れが全身を伝った。
今日だけで彼は、数年分の経験を積んだような気がした。