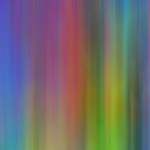薄く黄色い光は、太く、真っ直ぐと敵のロボットへ向けて宙を駆けた。
その光にほんの少し遅れて、凄まじい轟音が辺りの空気や地面を揺らした。
それまでそこにあったはずの丘は、原型を留めておらず半円形にえぐり取られており、しかも土がすっかり焦げてしまっていた。焦げた土の所々は赤く、未だ灼熱であり続けている。
対して問題のロボットは原型を留めている。
しかし、地面を抉り取るような威力の砲撃に耐える、屈強な防御力を、相手のロボットが持っているわけではない。
友里は主砲を撃つ直前、照準をわずかにずらして直撃しないようにしたのだ。
そんな訳で、敵のロボットは至近弾により駆動系をダメにされてしまい身動きが取れなくなったが、大破は免れた。
敵の命さえ、彼女は守って見せたのだ。
「ふうぅ……………」
深いため息を漏らし、友里は背もたれに身体を預けた。
まるで一生の中でもっとも難しい試練を乗り越えたかのように、ぐったりした。
実際、彼女にとってこれは試練だった。
生と死。
彼女が攻撃しなければ、2人そろって死ぬ。
逆に主砲を容赦なくうてば、自分たちは助かっても、相手は死ぬ。
彼女にとって自身の選択は最適解であった。
「……………終わったのか?友里?」
奏汰はカメラアイが捉えた映像に視線を向け、それから視線を落として友里の、水色の綺麗な髪を見つめた。
友里は彼の声に応じて、振り向いた。
「うん。これでもう大丈夫だと思う」と安堵した表情を浮かべ友里だったが、すぐに真顔に戻り、モニターに視線を映した。「たけど、まだ、確かめなくちゃいけないことがある」
友里は操作レバーを握り直した。彼女の操縦によりフライアは歩き出し、徐に敵の黒いロボットの腰につけられた箱を掴むと、ロボットから引き剥がした。
するとその中はこちら同様、コックピットになっていて、男が1人座っていた。
どうやら、彼がこのロボットを操縦していたのだろう。
「あの人に、ちょっと聞きたいことがあるから、ちょっと降りるね」と友里は梯子に手をかけた。
「ま、待てよ!」
それを引き留めたのは奏汰だった。
しかし、次に何を言えばいいのか彼には分からなかった。
友里は言葉に詰まる彼を見つめて、優しく笑う。
「大丈夫。もう何もしてこないから」
梯子を上り、ハッチから顔を出し、フライアの手に飛び移った。その後ろに奏汰もついてきており、同じように飛び移った。
自動で駆動することの出来るフライアはゆっくりと友里を地面へ降ろした。
奏汰を安心させるために優しく笑いかけた友里であったが、実際には彼女自身も安心できなかった。
もう敵に戦力も戦意もないというのは、彼女の希望でしかなかった。
2人は恐る恐る、ロボットの方に近づいた。
コックピットに居るのは、ピッチピチの服を着た若い男。体格はよく、筋肉が浮き出ている。奏汰と友里に気が付き、顔を上げた。
やせこけた頬に、刈り上げた頭部が特徴的であり、人相は悪く、人を殺すような鋭い眼を2人に向けた。
「動かないで。動いたら、今度こそ貴方の命はない」
脅すような口調で言う。
が、その必要もなかった。
対艦長距離連装粒子砲(ラグナロク)の威力は凄まじく、至近弾程度だったのにも関わらず、彼の身体にもダメージを与えた。
もはや彼に戦う能力など残っていなかった。
「何のようだ。笑いにきたのか?」
低い声で唸るように、友里に問いかけた。
それに対して「ううん」と友里が首を横に振る。
「いくつか訊きたいことがあるの」
男は目を細めた。
「答えると?」
「答えてくれたら、貴方も、貴方のお仲間も、皆助ける。どのみち、この騒ぎじゃ警察が来るわ。お互い、人に存在を知られたらまずいよね」
声が震えないように気を配りながら友里は男に再度問う。
奏汰は彼女の後ろからじっと見守る。
「無駄だ。俺も、仲間も、もう助からない。そうなっているんだ」
男は、ぐったりと背中を座席にもたれかかった。
その様はまるで、人生を諦めた人間のように覇気がなかった。
「貴方も仲間もまだ助かる。手当てをすればこれくらい」
「………分かっていないな。俺は仲間を売ったりしない。ボスの事も組織のことも話さない。諦めろ」
「なんで友里を襲ったのかだけでも教えてくれ!」
今まで黙っていた奏汰が、友里と肩を並べ、口を開いた。
「……その女は、脅威になる。それだけだ。それ以外は喋らん」
気だるそうに男は答えた。
「貴方は……………」
友里が次に質問しようとしたその時、バンッと公園内に響くような轟音が3人の耳を刺した。
「何だ!?」
辺りを見回すと、20メートル離れたところで地面に伏せる人の影。
こちらに何かを向けている。それは銃のように見えた。
音が鳴るまで、奏汰も、もちろん友里も気が付かなかった。
敵の仲間の1人がまだ動ける状態で、しかも銃で友里を狙っていることなど。
それを認識したのとほぼ同時、左隣に居たはずの友里が、気絶したかのように、ドサッと地面に倒れた。
「え………?ゆ………り……………?」
奏汰は膝をつき、彼女の肩を揺らして見せると、はっと息を飲んだ。
地面に伏した友里の腹部から、何か液体が漏れているのだ。
最初こそそれが何であるかは分からなかったが、月明かりに照らされると、嫌でも理解した。
「血……………これ……………血?」
紅いそれは、友里の身体を流れていた血であった。
「ま……て……。そんな!」
奏汰がばっと頭を上げると、撃った本人がこちらに銃を構えていた。
「!!」
━━━また撃たれる!
そう直観的に感じた奏汰は傷を負った友里を守ろうと抱きしめる。
身体は強張り、キッと目を瞑り、歯を食いしばった。と同時に先ほどの銃声が再び鳴り響いた。
しかし、カンッと何かに当たったような音がして、弾が奏汰や友里に来ることはなかった。
恐怖に押しつぶされそうになりながらもそっと目を開けると、そこにいたのは今まで奏汰の後ろに控えていたフライアであり、2人の壁となり、射線にならないように動いてくれたのだ。
「た、助かった………」
安堵したのもつかの間、フライアはいきなり両手で友里を抱えると、どこかへと走り去ろうとした。
「え、ちょ………!」
どうやら、奏汰の事など微塵も気にしていない様だった。奏汰は全身に残された力を振り絞り、フライアの脚部にしがみついた。
丁度、彼の手に収まるくらいの手すりが脚部にあり、そこには人ひとりが乗れるようなスペースがあった。
フライアはそのまま両脚に備えられたキャタピラを高速で回転させ、全速力で後退した。
奏汰は、身体を叩く勢いで迫って来る風に恐怖を覚えながら、それでも友里のことが心配で死んででもこの手を離さないと、冷たいボディーに必死にしがみついた。あまりの恐怖と押し寄せて来る風圧に声を出すこともかなわなかった。チラッと、先ほど撃ってきた人影を見た。
暗くてよくは見えなかったが、発砲してこないところをみると、恐らくは諦めてくれたのだろう。
公園内を颯爽と駆け抜け、小さい子向けの遊具がいくつもある遊び場をあっという間に通り過ぎてしまった。
やがて、十分に敵との距離を取ったと判断したフライアは湖のそばにある緑の生い茂る広場にたどり着き、そこでゆっくりと友里を降ろした。
月明かりは水面に映え、湖の上に光の橋を形作っている。
風が吹き、ゆらゆらとその光は揺らいでいる。
そんな幻想的な場所で、友里は土と草の上にぐったりとしている。
出血はまだ続いている。
「友里!!」
脚部にしがみつづけていた奏汰は、ひょいっと地面に降り立ち、両膝をついて友里の肩を掴んだ。
「おい!しっかりしろ!おい!」
痛みに顔を歪めてはいるが友里は、「はぁ………はぁ…………」と呼吸を荒くして、パクパクと動いている。
目も微かに開いている。
まだ、生きている。
しかし、それがいつまで持つかは分からない。
「しっかりしろ!友里!!」
必死に呼びかけ、友里の意識を途切れさせまいと奮闘していた。
「待ってろ!今、救急車呼ぶから!」
そう言って焦る手でスマートフォンを取り出し、指をひどく震わせばがらも一度110番を押して、消して、119番を入力した。
電話をかけ、耳に当ててみる。
しかし、いくら待っても繋がることは無かった。
画面を確認してみる。
通常、電波があればアンテナが4本は立っている。
それなのに、こんな大事な時に、アンテナは1本。
「くそっ!!!何で繋がんないんだよ!!!!!!」
焦りはイラつきに代わり、スマホを振り下ろした。
「た、多分、妨害電波の、せい…………」
苦しそうな声で、友里は軽く頭を浮かせた。
今では何処に行ってもスマートフォンで連絡そのものは取れる。ましてやここは自然公園。電波が繋がらないはずがなかった。が、しかし妨害電波が出されているとすれば話は別だ。
「友里!」
彼女は目を開き、奏汰の顔を見つめている。
「大丈夫。すぐに病院に連れて行けば、こんな怪我ぐらい…………」
奏汰はそう言って励まそうとした。でも、友里は自分の死を悟り、ゆっくりと首を横に振った。
「ごめんね………。私は、もう、助からない………」
「そんなこと言うなよ!まだ助かるって!大丈夫、俺を信じてくれ!必ずどうにかするから!だから………!」
奏汰の声は震えていた。
彼の目尻には熱いものが溜まっていく。
━━━まだ何か出来るはずだ!絶対に死なせない!
彼はすべての神経を研ぎ澄ませ、彼女を助けるための方法を考える。
考える。考える。考える。考える。考える。考える。考えろ!!!!!!
もう助からないかもしれない、間に合わないかもしれない、そんな絶望の可能性を理解はしている。それでも奏汰は諦めることを拒んだ。どうにかしなければいけない、自分が何とかしなければいけない。自分にも何か出来るはずだ。決して、友里を死なせるわけにはいかない。
「………ねぇ、奏汰。実はね、もう一つ、隠していたことがあるの」
優しく微笑み、まるで小さい子に語り掛けるような声の調子で友里は口を開いた。彼女のか細い右手を、奏汰の頬に添えながら。
「………何だ」
目の下をピクピクと震わせながら、奏汰は友里の言葉を待つ。
「奏汰が、好き」
………………………………意外な言葉だった。
「は………なに……………言って」
一瞬、自分が何を言われているのか分からなかった。
だから、無意識にそう返さざるを得なかった。
10数年、一緒に暮らしてきた中で彼女から初めて聞いた言葉。
「小さい頃から、奏汰が好き。いつも、隣にいてくれるところが好き。面倒くさそうにしてるのに、ちゃんと研究を手伝ってくれるところが好き。意外と人に優しいところが好き」
ずっと聞きたかった言葉。
「い、いきなり何言ってるんだよ………。今、どんな状況か分かって言ってるのか………!」
「ごめんね。ずるいよね。ごめん。でも、言いたかったことなの。私はずっと好きだった。私の大事な………大好きな人」
もう自分には時間がない。
その事を悟った彼女は、自分の想いを彼に伝えう決意をしたのだ。
自分の想いを吐き出した彼女は、心に貯めていた感情も決壊した。人形のように可愛らしい顔に、白い頬がわずかに赤くなり、涙が流れる。
その姿を見て、奏汰の目からも一粒、また一粒と大粒の涙が溢れだし、友里の頬にポタリと落ちる。
2人の涙が友里の頬で一つの流れになる。
「奏汰のことを心の底から好き。好きで溢れてる…………」
奏汰は顔をクシャクシャにしながら、泣いている。
「だったら!」奏汰は溢れてくる想いを抑えようと必死だったが、堪えきれず彼の頬に触れる友里の手をギュッと握った。
「だったら俺も言う!好きだ!友里!俺も、小さい頃から好きだ!ずっとそばに居たいくらい好きだ!周りに流されないところが好きだ!自分の好きなことに前向きなところが好きだ!研究で周りが見えなくなるぐらい夢中になるところが好きだ!困っている人間を助けようとあれこれ必死に考えるところが好きだ!意外におっちょこちょいなところが好きだ!」
次々と溢れてくる言葉、どれだけ吐露しても、尽きることはない。
「奏汰………奏汰…………」
友里は自分の愛する者の名前を呼ぶ。涙を流しつつも弱々しく笑顔を浮かべ、自分と同じように涙にまみれた大好きな人の顔を見ている。彼女の脳裏には今までの奏汰との思い出が、スライドショーのようにいくつも浮かんでくる。初めて出会った日。一緒に実験をした日。一緒に歩いた並木道。友里が無くしてしまったものを、泥だらけになりながら探し出した奏汰の姿。友里に笑いかける奏汰。
「友里……!友里………!」
奏汰もまた、自分がこの世界で最も愛するその名を叫ぶ。顔はクシャクシャで、次から次へと流れる涙を拭きとろうともせず、ただ大好き大好きで仕方がない人の笑顔を見ている。彼の脳裏では友里と過ごした記憶が、壊れたテレビのように次々と浮かんでは消え、浮かんでは消えを繰り返していた。初めて一緒に学校へ登校したした日。桜の木の下ではしゃぐ友里。実験に失敗して真っ黒になった友里。奏汰にだけしか見せない、友里の本物の笑顔。
「私はずっと前から…………」
ずっとずっと言えなかった。言いたかったこと。2人の関係を壊してしまうことを恐れ、胸の奥にしまっていた言葉。
「俺はずっと小さい頃から………」
この言葉を考えるだけで、胸が高鳴り、顔が熱くなり、恥ずかしくて空いての顔を見れなかった。それでも平静を装って、相手に気取られないように、慎重に隠していたこの想い。
やがて2人の声が重なった。
「奏汰が好き……」
「友里が好きだ!」
生死の恐怖を肌身で体感した少年と少女は今夜、一生に一度だけの愛を叫んでいるのだ。
此処は世界で最も美しく、儚い物語の舞台。
脇役である星たちは、この悲劇的で美しい絵画に涙を流し、瞬いた。
月は2人の最期のひと時を見つめていた。これからの未来を見ているのか、悲しそうに模様を歪めている。光は一層明るく、湖にくっきりと反射している。
「頼むから俺と一緒に生きてくれ。死なないでくれよ…………!」
「さようなら。奏汰…………。彼女を………お願い………」
友里は最後の力を振り絞って、自身のペンダントを彼に差し出した。
「これを、受け取って……………」
奏汰が彼女のペンダントを受け取ると、ドサッとそれまで奏汰の方に伸ばされていた手から力が抜けた。
友里の呼吸が浅くなっていく。
奏汰の唇が震える。
「いやだ!ダメだ!友里!友里!!」
友里の瞳が閉じていく。
ゆっくり、ゆっくりと。
傷口からは血という血が流れ、大地に染みていく。
これから迎えるそれに恐怖を感じているはずなのに、友里の表情は、人生で最も満ちたりた、優しい笑みを浮かべていた。
肌から血の気は失せていき、最終的には彼女の心臓の鼓動さえも衰え、ついには止まってしまった。
「ああ!あああ!あああああああ!!」と嗚咽を漏らす。
叫びにならない叫び声が、薄暗い夜空に吸い込まれる。
この日、1人の少女は息絶えた。