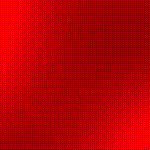朝。小鳥たちの楽しそうなさえずりがあっちこっちから聞こえてくるが、その姿は見えない。
きっと木の葉に隠れて遊んでいるか、餌を探しているのだろう。
ここは街の端にある森。普段、あまり人が立ち入らない場所。しかし今日は、そんな自然の中にそぐわない影が、そこにはあった。厚く頑丈な装甲に身を包んだロボット、フライアが、木に身を潜めている。
フライアの暗いコックピットの中で、奏汰の寝息がゆったりとしたリズムを刻んでいる。昨日の夜、友里との別れの悲しみを拭いきれず、また、世界で自分しかいないような、孤独な気分に飲まれてしまい、一晩中啜り泣いた後、眠ってしまった。
その姿はまるで幼い子供のようであった。
朝になるまでコックピットは暗かったが、外で太陽が顔を出し空に昇っていく頃には、外の様子を映し出す画面がついたことで一気に明るくなった。
さすがに眩しく感じたのだろう。彼は、やがて、目を覚ました。
寝ていたとはいえ、座った状態だったし、あんなことがあった後だったから、質の良い睡眠とはいえなかった。
そのせいで、寝起きの奏汰は酷くボーっとしていて、霧がかかったみたいに頭の中がはっきりとしない。その上、腕を枕代わりにしていたせいで、血流が悪くなって手の先の感覚がないほど痺れている。
きっと、今まででもっとも目覚めの悪い朝だろう。
ようやく目が慣れてきて、画面の向こう側の景色を認識した。
フライアの目の前を流れる河は、太陽の光を元気に反射しており、チラチラと眩しい。
夜は不気味に見えていた木々も、緑色の葉で青々としており、奏汰はその生命力を感じ取った。
ここでは、人間以外のものが生きているのだ。
「朝、か……………」
両手の痺れが治まるのを待ってから、奏汰は操作レバーに手足が引っかからないように気を付けながらハッチから外に出た。
コックピットから飛び降りると、地面に着地した瞬間に足に衝撃が伝わり、痛くて目に涙を浮かべた。
「あ…!っ!…………痛てて」
足の痛みに顔をしかめていると、さっきモニターで見ていた景色と同じ姿が、目の前に広がっていた。
昨日の出来事が全て夢か幻だったように、素晴らしい心地だった。
風が優しく彼の頬を撫でた。
空は雲一つなく青い。降り注ぐ日の光は熱い。
河の流れる音は、聞く者の心を癒す。
「まったく。やっと起きたんだね?」
しばらく奏汰がその場で動かないでいると、後ろから、聞き覚えの無い、おそらくは奏汰と同い年くらいの少女の声がした。
━━誰だ!?
奏汰はバッと振り向いた。
しかし、そこには人は居なかった。
代わりに黄緑色と白を基調とした、奇妙なロボットが立っていた。
フライアだ。
昨日は暗くて分からなかったが、このロボットはかなり屈強な造りをした見た目をしており、両肩には武士の鎧のようなカバーを付けている。
腕は細くはないが、特別太いわけでもない。
しかし、脚の方はかなり太く、どこが膝なのか判別しづらい。
腰には何やら箱のようなものが左右に備え付けられており、それぞれ2つずつ穴が開いている。
さらに顔には目、鼻、口に当たる部分はなく、下半分は白く、上半分は黒い。
黒い部分にはカメラがあるようで、薄っすらと大きな瞳のようなレンズが見える。
胸元は大きく出っ張っており、コックピットはここに位置している。
奏汰はフライアの左右を確認した。
しかし、声の主らしい女の子の人影は見つからない。
「あれ?確かに声がしたのに……………。おかしいな」
「何がおかしいの?」
再び、女の子の声がした。
「うわ!!」
奏汰は思わず尻餅をついた。
なんと、少女の声はフライアが発していたのだ。
「だ、誰だ!?誰か乗っているのか!?!?」
「誰って……………失礼だなぁ。あたしは思考人型機動戦車I-903『フライア』だよ?」
「ふ、フライア……………!?」
なんと、少女の声は、自分がフライアであると主張しだしたのだ。
「馬鹿言うなよ。フライは、ロボットで、口を利くなんて…………。分かった、コックピットに誰か乗り込んだな?出ておいで。君の乗るようなものじゃない」
子供か誰かが誤って、もしくはフライアが乗せてしまったのだろう。そうでなきゃ、さっきまで無言で機械的に動いていたフライアが話すはずがない、これが彼の出した結論だった。
「私には元々、自律思考型AIが搭載されてるの。今朝、やっと言語の初期設定を終わらせたんだ」
可愛らしいその声は、なんだか難しそうな単語を並べている。
奏汰は信じることが出来ず、「いい加減にしろって………」と、言いながら、フライアの脚部を足場にして、ひょいっと腰や腕に掴まって、コックピットの上部ハッチに手をかけた。
ハッチから中を覗くと、そこには無人の座席。
誰かが乗っているわけではなかったのだ。
「な!?そんな馬鹿な!?うわっ!」
驚きのあまり手が滑ってしまい、奏汰は背中から落ちてしまった。
建物の2階ほどの高さのあるコックピット。打ちどころが悪ければ怪我では済まない。
「わ!」
一瞬、心臓が浮き上がるような感覚のした後、奏汰は硬い何かに包まれるような感覚を覚えた。
冷たい嫌な汗がどっと溢れ、数秒もないうちに引いていく。
「もう、気をつけて。人間は簡単に死んじゃうんだから」
奏汰がゆっくりと目を開けると、彼の身体はフライアに抱きかかえられていた。
カメラアイがじっと奏汰を見ている。
「あっ、ぐっ、お、降ろせ!」
「はいはい」
奏汰の要望通り、フライアは白や灰色の小石の絨毯の上に彼を降ろした。
「………お前、本当にフライア、なのか?」
「そうだよ?」
あっさりと応える少女の声。いや、フライア。コックピットが無人であることと、周りに少女らしき人がいないこと、そして声のする位置からして、フライアが言語を習得して、こうして会話していることは明白だった。
まだ信じられない、と疑いの念の晴れない奏汰だったが、しかしこのような状況を突きつけられたら、嫌でも信じなくてはいけない。
結局、奏汰は受け入れた。そして一つ、疑問が生まれた。
「なぁ、それは、友里がつけた機能なのか?その、会話が出来るって」
ピクリッとわずかにフライアの首が上下に動いた。
「それも、そう。元々は人間と連携をとって作戦遂行できるように設計されてるから。でも、昨日は戦闘用システムの方を最優先で初期設定をしてたからこっちの設定が遅れちゃった………」
昨日まで黙っていた彼女が嘘のように、次々と言葉を並べてくれる。
「あ、まだあなたの事パートナーだって認めてないからね?あれこれ命令したり、私を思い通りに操縦しようとしないでね。コックピットもあまり乗らないで」
「は?え?」
何を言っているんだ?という顔で奏汰はフライアを見つめ返した。
「パートナーってなんだよ?」
「そのペンダントの所有者。私の所有者。私に乗って共に行動する搭乗者。パートナーと私は、一心同体になって敵と戦うの。開発者様(小黒友里)が貴方をパートナーとして登録しちゃったから、仕方なく従ってたけど。こうして言葉が話せるようになったおかげで、貴方の命令を明確に拒否できるようになったの」
なんてことだ。と奏汰は驚いた。首から下げている青いペンダントを握ってみる。昨晩は確かにこれを用いてフライアにあれこれ指示を出してしたが、まさかそんな意味があったとは思わなかったのだ。
それに、友里が奏汰をパートナーとして登録したことについて、訊かずにはいられなかった。
「友里が登録したってどういうことだよ」
「そのままの意味だよ。開発者様(小黒友里)は貴方にペンダントを渡すとき、生体認証を登録できる状態にしたの。貴方の指紋、声紋、虹彩、顔、DNAを全て登録されちゃったの」
「あの時、そんなことしてたのかよ………あいつ」
悲しみはどこへ行ったやら、友里らしいといえば友里らしいな、と奏汰はわずかに広角を上げた。
奏汰は俯いた。そして顔を上げた。
「このペンダントがある限り、お前は俺の命令を聞くんだろ?」
「お前じゃなくて、フライア」
語気は強くはないが、訂正を求めるフライアの雰囲気はほんのり怒りが混じっていた。
「フライアは、俺をパートナーとして認めてないって言ったな、さっき。話せるようになって、命令を拒否できるようになったって。でも、説明を聞く限りは、ペンダントの持ち主、つまり俺の命令に従うように造られているはずだ」
「かならずしもそうじゃないの。私もあまり理解はしていないけど、私にはある程度行動の自由がある。武器使用は特定の条件を除いて、パートナーの許可がないと使えないけど、それ以外なら……………」
奏汰は黙り込んだ。一体、なんで友里は自分にフライアを託したんだろう。そしてこのロボットは何故か自分を嫌っている。この点が彼にとって謎である。昨日の夜は従順に命令に従っていたはずなのに。分からない。分からない事だらけだ。ずっとそうだ。友里の家がアンドレと呼ばれる組織に襲われた時からずっと。いや、それよりもずっと前からだ。友里は奏汰の幼馴染であり、好きな人。
彼女は幼い頃、前世の記憶を取り戻し、自身の持ちうる科学の知識を駆使して何度も何度も何かの研究をしていた。そしてそんな天才の彼女は奏汰のことをずっと好きでいてくれていた。
2人は思いを伝えるのが遅かったが、確実に両想いのまま長い時を一緒に過ごしていた。
「なぁ、フライアは俺が嫌いなのか」
ふと奏汰が問いかける。
どんな風に返答するだろうか、と思考を巡らせていると、数秒も立たないうちに返事が返ってきた。
「え?いや別に嫌いとかではないけど」
「は?じゃ、どういう?」
どういう理由で?と言葉は続かなかった。
なんとなく、友里に託されたフライアに嫌われているわけではないという安心感が、彼のどうしてという疑問に勝ったのだ。
それにこのロボットに搭載されたAIは優秀なようで、彼が何を訊きたいのかをすぐにくみ取った。
「私と貴方はまだ、出逢って短いから。いくら開発者様(友里)の記憶と人格があるからって、私は私で貴方を判断したいの」
ここでまた、奏汰の頭に引っかかることを、このフライアという機械仕掛けの女の子が言った。
「開発者様って友里のことだよな。あいつの記憶と人格があるってどういうことだよ」
同じ体格の人間同士であれば顔を近づけて問い詰めるような勢いで、奏汰は質問した。
フライは若干、後ろに仰け反りながら答えた。
「私には開発者様(小黒友里)の記憶と人格をインプットされてるの。彼女が何を考え、何を想い生きてきたのかを、私は知ってる」
奏汰は息を飲んだ。喜びとも驚きともつかない表情をしている。いや、今まで友里が何を考えていたのかを知ることが出来ると考えれば、奏汰にとって喜ばしいことなのかもしれない。しかし、友里がそれほどまでに卓越した化学技術に驚いたのかもしれない。そもそもこの出来事自体にはっ驚いたのかもしれない。
「あ、あいつが何を考えていたのか知っているのか」
先ほどよりも、より食いつかんとばかりに質問する奏汰。その姿は一種の変態にも思われるような食いつきっぷりだった。
これにはさすがにフライアも引き気味だった。
「知ってる。けど、教えない!」
「な、なんで!教えろよ。いや、教えてください、この通りです!」
勢いに任せて奏汰は頭を下げた。
「女の子の気持ちを、そうやって簡単に聞くものじゃないと思うよ?それに故人の………」
なんと、フライアに、ましてや機械で心や身体が造られているこのロボットに、人間である奏汰が説教されてしまった。
奏汰はなんだか自分に対して、恥ずかしい思いをした。
「そ、それは、確かにそう……。だけど」
だけど、それでも知りたい。そう望むことを諦め、口をキッと結んだ。
「とにかく、私が貴方がどんな人間か見極めてから、パートナーとして認めるかどうか決める。それまではコックピットにも乗らないで。ほら、あまり知らない男の子を家にあげたり、部屋に招いたりしないでしょ」
「いや、え、どうだろう…………」
奏汰は、友里の家には数えきれないほど入り、人の家とは思えないほど寛ぐこともあったし、友里もそれを良しとしていた。
友里以外の女子の部屋に入ったことは、幼い頃に片手で数えるほどしかない。
何も答えないまま下を向く奏汰を見かねて、フライアはため息を漏らした。尤も、彼女には口はないので、声でため息を表現しただけだったが。
「ところで、さっきから何かが震える音がしてたけど?」
「え…………」
フライアに言われて、奏汰はズボンのポケットに手を突っ込む。
右ポケットにある四角い板が手に触れる。それを取り出してみると、それは黒いスマートフォンだった。通知を知らせるランプが点滅している。
電源ボタンを押すと、何通ものメールと着信通知がロック画面に表示された。
中には留守電も入っていた。
「やべ、連絡しないまま寝ちゃったのか」
すぐに留守電のバーをタップして、スマホを耳に当てる。
「4件の新しいメッセージです。1番目のメッセージです。7時18分。『ちょっと奏汰!あんた今どこにいるの!?隣で何があったの!?友里ちゃんの家壊れてるし、それに友里ちゃんが……………。とにかく帰ってきなさい!!』」
自動音声が流れたあとに、泣き出しそうな声で帰ってくるように訴える母親の声。
他の留守電も同じ内容だったが、後の方になるにつれてその声は悲痛なものになっていた。相当、奏汰のことを心配しているようだった。
「………………メッセージは以上です」
そっと奏汰はスマホを耳から話すと、すぐにメールで「すぐに帰るから待ってて」と送信した。
風が吹き、辺りの木々の枝を揺らし、葉と葉がすれる音がした。
スマホをポケットにしまい込んだ奏汰は、フライアに向き合った。
「俺、行かなくちゃ。フライア、人に見つからないようにここに居てくれ」
そう告げて、奏汰は走り出した。