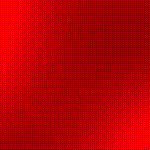次の日の朝、奏汰は友里の家へ行き、玄関に入ると彼女はダボダボな白衣を着たままラボで寝ていた。スヤスヤと可愛い寝息を立てている彼女を起こすと、寝ぼけたまま手をひらひらと振って、「研究がしたい」と言い出した。こういう時、小黒友里という人間は梃子でも動かない。仕方なく学校には体調不良という名目で休む旨を電話で、奏汰が伝えなければいけなくなった。というのも、彼女の親はこの日は帰ってこない日であり、彼は親の振りをしなけらばならなかった。奏汰は固定電話の受話器を取った。もちろん、ここでも友里の技術力が役に立つ。受話器には変声機能が友里によって取り付けられており、奏汰は親の振りをして、親の声で電話することが出来るのである。こうして、友里の今日の学校は休みになった。
「お前、明日は来いよ?」
「ん~。分かってるよ。今日だけ今日だけ~」
相変わらず寝ぼけながら、友里は答えた。
すっかり呆れた奏汰は、友里を抱えてベッドまで運んでから1人で登校することとなった。
1人で歩く通学路は味気なく感じ、ワイヤレスイヤフォンで音楽を聴きながら早歩きで学校に向かって歩いていた。
とあるアニメのOPソング。それは朝に聞くにはピッタリなほど元気な曲で、この世の絶望や不平不満など全て吹き飛ばしてしまうようなもので、友里と登校しない日はいつもこの曲を聴いている。
イヤフォンはワイヤレスであり、コードに身体をまとわりつかれる煩わしさがない。
大好きな曲を聴きながら、太陽の光に反射する家々の屋根を眺め学校へ登校するために歩く小学生の列を眺め、ついには空を見上げた。
元気な声が響き渡り、その道を通る誰もが生き生きとしていた。
空はこの上ないほど快晴であり、友里も折角の晴れなのだから、家から出てこの綺麗な青空を見ればいいのに、と奏汰が思ったほどである。
「………太、おはよう、奏汰!」
曲の2番のサビに入るところで、後ろから名前を呼んでくる朗らかな男の声がした。
イヤフォンを外して、振り向いて確認すると、そこにいたのは2人。髪型をキザに整えた友樹と、その横にいる花蓮。
彼らもまた、毎朝のように一緒に登校している仲なのだ。
「やっと気づいたぜ。お隣さんの彼女は今日は欠席?」
「友里は彼女じゃないし、その通りで欠席」
「そっか。じゃあ、3人で行こうぜ」と無を言わさず、奏汰の肩を組み、歩み始めた。
やれやれといった表情で花蓮はそれを見ていて、いつもの事かと奏汰も諦めてイヤフォンをケースに入れて、ポケットに突っ込んだ。
「友里ちゃん、出席数大丈夫かな。もうかなり休んでるよね」
「どうなんだろ。どうにかなるといいけどね」
友里とは中学からの付き合いで、唯一同性の友達である花蓮は心配そうに言うと、それに対して奏汰は、軽く答えた。
実際は、彼も友里の出席日数については心配しており、留年するんじゃないかと何度か尋ねたが、当の本人は大丈夫大丈夫と返すだけだった。
奏汰は「本当かよ………」と半分は疑っていたが、彼女のことを信頼してもいるため、本人が言うならきっと大丈夫なのだろうと、結論付けていた。
「なあ、奏汰。今朝のニュース見たか?」
2人の会話が終わったことを確認してから、友樹は奏汰に本日一番に話したかった話題を振った。
「いや、今日はそんな余裕が無くて。何かあったの?」
「これだよ!これ!」
友樹は自身の赤いスマートフォンを胸ポケットから取り出し、画面をタップして何個か操作し、今朝のニュースの記事を見せた。
「これって………」
そこに映し出された記事の見出しには『工場襲撃事件!防犯カメラに映ったものは…………』 と書かれていた。その下には「正体不明のロボットか!?」とさらに読者を引き付けるための文言が添えられていた。
「一昨日、工場が襲撃されたらしいんだけど、防犯カメラに変なものが映ってたらしいんんだ」
「このロボットってやつ?」
「そうだ。動画もあるんだぜ?」
奏汰と友樹、それから花蓮は立ち止まり、そのネット記事に添付された動画を開いた。
映像は夜に撮られたものであるため、非常に暗かったが人物などはそれなりに見える。
十数秒の間をおいて、今回話題になっている工場が不審な爆発をした。
原因は何かと奏汰が考えていると、ニュース動画は編集により工場が爆発する前に巻き戻され、建物の奥にある林をクローズアップした。
赤い輪が何かを囲んだ。
動画を止め、目を凝らして見てみるとそれは大きな人型の形をした、でも人とは決定的に異なったものが映りこんでいた。
「これがロボット?よく分からないな…………」
奏汰は眉をしかめた。
確かにロボットと言われればそう見えなくもない。しかしながら、この解像度の映像だけでは確証に足るものではないと言わざるを得ない。少なくとも素人目線からみればそうだ。
動画をもう一回再生すると、そのロボットらしき影は一瞬で飛び跳ねて、どこかへ消えてしまった。
そのすぐ直後、工場が爆発した。
少なくともこのロボットらしき影と、工場の爆発は絶対に関係がないとは言い切れない。
友樹は若干興奮気味に口を開いた。
「政府関係者の意見が出てて、自衛隊の装備とかではないらしいんだ。もちろん海外でもこの手のロボットを開発しているなんて情報はない。もしこいつが本当にロボットなら、相当凄い技術だろうぜ。何せで建物2階分ぐらいありそうな巨体であり得ない速さで移動しているからな」
「お前、こういうの好きだっけ」
鼻息を荒くして早口気味に言う友樹に対し、若干呆れながら奏汰が訊ねた。
「ロボットは男のロマンだろう。今まで何見て生きてきたんだ?」
「お前なぁ………」
「冗談はここまでなんだけど」と、興奮していたのが嘘かのように、友樹は真剣な面立ちとなり、奏汰の顔を見つめた。「言った通り、ロボットをここまですばしっこく動かすのは現代の技術では不可能だ。しかもこの工場、ここからそんな離れていないみたいだ。一応訊くけど、このロボット、まさか小黒のものじゃ………」
「はぁ?そんな訳………」
即座に反応しようとした奏汰だった。しかし、すぐにそれはある記憶によって引き留められた。友里のラボに置かれた灰色の布。中身が何かは分からないが、布越しでもゴツゴツしたものであることは確かで、しかも建物2階分ある。
「………古谷君?」
言葉に詰まっている奏汰に対して、花蓮が呼びかけた。
「あいつが、友里がそんなことをするはずがないよ。あいつが作るモノって言えば変な、使えないやつばっかりだし…………」
取り繕って、出来るだけ友里への疑いを晴らそうとしている奏汰だが、その声は微妙に震えていた。
「ごめんな。別にめっちゃ疑ってるわけじゃない。小黒が工場を襲う理由もないしな」
申し訳なさそうに眉毛を片方だけあげて、頭を下げる代わりに肩をすくめた。
ほっと奏汰は胸をなでおろし、代わりに今の時間が何時か気になりだした。
「あれ、今何時?」
友樹がスマホの時計を確認すると8時17分と表示されており、遅刻ギリギリの時間となってしまった。
「うわっ。やばいじゃん!!」
3人はリュックを背負い直し、遠くに見える学校目掛けて走り出した。
今日の教科は資料集や教科書を使うものが多く、奏汰や花蓮など、真面目に荷物を持って帰るような生徒にとってはかなりの重荷となった。
徐々に息が切れてくる。
6月といえば、真夏日ほどとは言わなくても走れば暑くて汗を大量にかくのに十分な気温である。
朝と言っても、照り付ける太陽の熱には誰もが額の汗を拭う。
学校に着くころには校門に生徒指導の先生が遅刻と服装を取り締まるために全校生徒の名簿を片手に立っていた。
学校で怖いと評判の先生。彼は彼の職務を忠実に全うし、遅刻した生徒の名前を聞き、名簿と照合すると担任の先生に報告するのだった。
3回遅刻をすれば、まず間違いなく生徒指導行きとなる。そのため、遅刻ギリギリに登校してくる生徒からすれば、天敵のような存在であり、校門を通らずわざわざ裏側の柵から侵入しようとする生徒も極一部だが存在する。
奏汰、友樹、花蓮は走りながら、服装を整え、他にも走って登校してくること生徒を追い抜いて、校舎へと走る。
時間的にギリギリ遅刻認定されず、生徒指導の先生から「もっと早く来いよー」と声をかけられる程度だった。
奏汰が振り向くと、彼らより遅く来た生徒は足止めを喰らって遅刻を取り締まられている。
もう少し遅かったら、あそこにこの3人も加わっていたことになる。
階段を駆け上がり3階、何とか教室につき汗を拭うと、重たいリュックをそれぞれの机においた。
教室の後ろ端、窓側の友里の席には当然ながら誰もいない。
隣の席では、奏汰が授業に使う道具の準備をしている。
「おやおや今日はいつもより遅れてきたな。それにあのマッドサイエンティストはどうしたんだ?奏汰くん?」
厭味ったらしく息切れしている奏汰に話しかけたのは、廊下側に座る健司だった。
「き、今日は休み……………」
「へぇ、そうかそうか。なぁ、もしかして一昨日のロボット騒ぎってのはもしかしてお前の彼女のじゃないの?あいつならへんてこなロボットぐらい作れるんだろ!」
未だに中学生の気分でいるこの阿呆(あほう)は、わざと大々的に叫んだ。
当然、その声に反応して他のクラスメイトが反応し、一斉に奏汰の方をみる。
「今日休んだのだって、犯人だからじゃないのか?」
さらに煽るように続けた。
普段なら、健司のこの人を馬鹿にしたようなふざけた言動は誰も耳を貸そうとはしないが、この時は「小黒友里ならやしかねない」という先入観が、この事柄に興味をひかせた。
人とコミュニケーションをとることを極力さけていた友里の態度が仇になったのだ。
「やっぱり小黒がやったんじゃね?」
「え、さすがに無いでしょ……」
「でも変な研究しているって噂だし」
「あの子、苦手だったんだよね」
「理系が得意だかなんだか知らないけど、お高く留まってる感じが嫌だったな。運動できないくせに……」
「やっぱ怪しいって。今日も休んだんだろ?」
奏汰の耳に入るのは、クラスメイトたちの本音。友里に対して否定的な意見。拒絶の声。
奏汰にとって、これほど憤慨するのは久しぶりだった。
幼馴染を、大事な友達を、ずっと一緒に過ごしてきた大好きな人をここまで言われて正気でいられるような人が、果たしてこの世にいるだろうか。
彼はどうにかして、弁明を図るべく大きく口を開いた。
「み、皆。違うんだ!あいつは確かに変なものを作っているけど、どれも役に立たないようなものばかりで、あんな巨大なロボットを作るなんてことは………」
「でもさー。実際に頭めちゃくちゃいいじゃん」
「先生の知識を圧倒したこともあったもんね」
「てか古谷って何かと小黒の面倒見てるよね」
「何か知ってるんじゃないのー?」
「庇ってるんだよ。あいつも向こう側の人間なんだよ」
非難の標的が小黒友里という存在から奏汰に移った。
こうなってしまうと彼一人で収集をつけるのは困難だ。
それなのにクラスの声は大きくなる一方だった。
「おいおいいい加減にしてくれよ皆!ちょっと頭冷やせって」
そんな騒音ともいえるクラス中の非難の声を押さえつけるように、友樹が奏汰の前に出た。
「よく考えてものを言えよ。俺らと年齢変わらねえ奴が、そんな上手く巨大ロボなんか作れるかよ」
「それに友里ちゃんに、工場を襲うような理由なんてないよ!!」
花蓮も奏汰や友樹の味方につき加勢した。
「分からないだろ。そもそあいつがなに考えているかも分からないじゃねえか!」
健司は噛みつくように、3人を睨みつけるように言った。
「わ、私は、違うと思います!!!」
黒板の方から違う女子の声がした。
クラス全員がその方向を向く。
視線の先にいたのは、黒髪をおさげ結んだ、眼鏡をかけた女子生徒。
彼女の名前は中野奈美(なかの なみ)。
比較的クラスでは目立たない分類で、おどおどした言動が特徴の女の子である。
「違うってなんだ?中野」
「小黒さんは、私が困っていたとき、助けてくれました。何度も。私はどんくさくて、背も小さいから図書館で読みたい本が高いところにある時、不思議な道具で取ってくれました。中間テストの試験勉強でも、分からないところを教えてくれたんです……………」
声は震えている。しかし、友里を庇いたい、守りたいという思いははっきりと伝わるほど、彼女の瞳は強い意志で、健司を睨みつけた。
「だから、私は、絶対に小黒さんが犯人ではないと思います!!」
健司は何も言い返さず、奈美を睨み返しただけだった。
教室内がぴりついた雰囲気に包まれ、仲が崩壊とまではいかないが、ある程度支障が起きそうだとはその場にいた誰もが思った。
そんな時、ガラガラと教室の前の方の入り口の戸が開かれる音がした。
同時に入ってきたのは誰よりも年上そうな男。
このクラスの担任である。
「おお。どうしたどうした。何か揉め事か?」
その一声に、あれだけ非難を浴びせていたクラスメイト達は今更ながら我関せずという態度をとり、それぞれ己の席に座った。
奏汰たちも何も無かったように席に着いた。
教室全体を見回し、状況をある程度察した担任は、ホームルームを開始し、「いいか?偏見や勝手な憶測で人のことを悪く言うな」とクラス全体を注意した後で、いつも通り1日の予定と連絡事項を伝えると、ホームルームを終えた。
こっそり奏汰を呼び出し、あとで職員室に来るようにと伝えた。
奏汰は身構えたが、担任の先生は優しそうな表情を浮かべて安心しろと一言添えた。