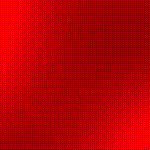杉田高等学校の校舎には約1000人もの生徒が、40人ごとに教室に入り、自分たちの席に座り、教科書を広げノートを広げ、教師によって行われる授業を聞いて、必要であればメモを取るし、指示があれば問題を解いている。
しかし一般的で真面目で優秀な大多数の生徒が、教師の理想とする授業態度をとるのに対して、少数の生徒はそうではなかった。ある者は、教師にバレないように教科書を立て、持ってきていたお弁当のおかずを音の立たないように細心の注意を払いながら頬張っているし、またある者は教師のことなど気にも留めず、自身の腕を枕として、大きくいびきをかきながら寝ている。
常習的に悪い態度を取るこれらの生徒を、教師たちは認識をしているものの、数回に1回は注意するのみであって、あとは真面目に授業を受けている生徒のために空いた時間で綿密に組み立てた授業を遂行するのであった。
しかしながら、そんな教師たちも一目おくような生徒が、あるクラスにいた。
『1年B組』というプレートが出入り口上部に掲げられた教室にいる生徒、小黒友里。
彼女は国語や英語、地理も歴史もからきし駄目だった。前回の定期試験では、これらの教科は赤点ギリギリであった。
体育も苦手なようで、身体的に男子よりも力がなく華奢である、というような言い訳ではもはや通用しないほど、運動音痴だった。他の女子と比べても、その差は歴然である。
もはや他の女子生徒の方がより男子的であり、この高校では女子の運動部が全国大会へと出場することがやたらと多い。
それゆえ知名度は高く、この高校で部活をし仲間たちと切磋琢磨し全国大会を目指そうと、志高く第一志望にする生徒も多いのである。
そんな熱意と志とは無縁な友里は、これらの事柄に加えて授業を欠席することも多かった。
体調不良や忌引きという理由をつけて、入学してまだ二か月だというのに、教室で真面目に授業を受けていることの方が珍しくなってしまった。
もちろん、体調不良や忌引き云々は、彼女が必要以上に目立つことを嫌ったためであり、本当の理由は「研究に没頭していて忘れた」だとか、「そもそも高校へ行って授業を受けることは苦手」などである。
担任の先生も不審に思っており「こいつの祖父母は何回亡くなってるんだ………」と独り言を言って頭をかきながら、それでも名簿帳に必要な記入を行っている。
いじめや、クラスに馴染めないのかという人間関係の線を疑って、担任の先生は1度、彼女に質問したことがある。しかし、その時も友里は適当な回答を並べるばかり、一通り話し終えたあとで遠慮がちな作り笑いを向けると足早に去っていった。
このように学校の授業に参加することが少なく、また英・国・社のテストの点が低く、おまけに運動神経も悪い彼女が、まだ高校1年生の中間試験という簡単なテストとはいえ、数学・科学を含む理系の教科で満点をとって教師たちが驚くのも当然だった。
アドバンテージが完全に理系に極振りしており、テストだけでなく、数少ない授業でも優秀である。
そんな彼女は担任の先生にだけでなく、誰かに話しかけられた時はいつも、なるべく人間関係を悪くしないように全神経を集中させて、相手とのコミュニケーションを丁重に断っており、相手から逃げた先はいつも古谷奏汰だった。
「まだ、他の人との関わりが怖い?」
学校からの帰り道、両手で頭を支えて空を見つめる古谷奏汰が、ふと、そんな質問をした。
「怖いっていうか。なんていうか……必要以上に関わらない方がいいと思って。ほら、私、変でしょ?色々と」
胸に手を当て、自嘲気味に友里は言った。
作り笑いもここまでくると、滑稽に思えてしまうだろう。
「いや、まぁ、文系科目はダメなのに、理系科目だけは全部満点取れるのはシンプルに凄いと思うし、変な研究ばっかりしてるけどさ」
そんな風に答える奏汰の声を聞いて、友里は少し俯いた。
「でもさ」と彼は続けた。「何かに没頭出来ることって凄いと思うぜ?それに研究に没頭してるときのお前は、その、楽しそうで、なんか、か、可愛いし………」と奏汰の声は段々と小さくなり、自分で何を言っているのか気づいた奏汰はそっぽを向いて、ボリボリと頬をかいた。
顔は紅い。耳も紅い。
友里は彼のそんな言動を見て一瞬の驚きの表情の後、笑顔になり「ふふ、ありがとう」と元気のこもった声で返した。その笑顔は高校生らしくも中学生の頃の幼さをほんのりと感じさせるような、本物の笑顔だった。
奏汰は振り向いて一言、言葉を添えた。
「だから、もっと自信持て」
自信をもって、もっと色んな人と関わって、学校生活も楽しんでほしい。
それが彼のはかない願いだった。
「………うん」
なんとも言えない雰囲気になった後、友里と奏汰は2人で、空に浮かぶ雲を眺め、家々の塀の上を音もたてずに歩く猫を可愛い可愛いと言いながら、雑談をして歩いた。
朝は働きに出かける人々を見守っていた太陽が、この時間になる頃には下校する学生たちを出迎えるように地平線の向こう側へと傾き、水色だった空をオレンジ色染めあげた
2人はそれぞれ自宅に着いた。
「じゃあ、後で家来て」
「わかったよ。あとでな」
もう日は傾いているものの、彼らは後でまた会うことを約束して、お互いに自分の家に入った。
学校から帰った後に、友里の実験若しくは作ったものを見せるために、奏汰が彼女の家に行くことが幼い頃からの日課になっていた。
一度だけ、奏汰がそのことを忘れてぐっすりと自室で昼寝をしてしまった時には、友里は少し不機嫌になりながら、黄色のコードをモバイルバッテリーに取り付けた摩訶不思議な手袋を使って、鍵がかかっているはずの玄関のドアを簡単に開けて入ってきて、起こした。
これにはさすがに奏汰も驚き、以後、約束を忘れることはなくなった。
今もこうして、黒い箱のようなリュックを自室の勉強机の横に置き、明日の時間割を確認して学校にもっていく教材を入れ替えた。やるべき事を一通り終えてしまうと、隣に行くために一度脱いだ靴をまた履いて、玄関のドアを開けるのだった。
「ほら、来たぞ」
お互いを信頼している2人の関係は誰よりも深い絆で結ばれており、そのためこんな風に奏汰が友里の家の玄関を開けて、あたかも自分の家のように振舞って入ったとしても、日常の一部にすぎないことなのだ。
彼女の両親は、ほぼ毎日家を空けている。
大抵、彼女は自分のラボにおり、迷いなく奏汰はそこへと向かった。
ラボ、というのは友里が実験やら研究やら行うために、1階と2階の間の床を無くし天井が高くなるようにリフォームされた、この家で最も広い部屋である。
ラボは床も壁も白く塗装されており、家具のように配置された棚には書籍類や実験器具、薬品が、埃も被らずに並べられており、窓ガラスの向こうから奏汰を見つめている。
その様子はまるで学校の化学実験室である。
「友里ー。いるかー?」
「はーい!ちょっと手が離せないから、そこの椅子でゆっくりしててー!お茶は入れてあるよー!」
奏汰の呼びかけに応じて、ラボの奥から何やらガチャガチャと音を立てる友里の声がした。
軽くため息をつきながら、奏汰は辺りを見回した。
部屋の真ん中に置かれている薄い黄緑色の細長い机の上は対照的に実験器具や資料が散乱しており、小さなスペースには緑色の液体の入ったビーカーが湯気を立てて置かれていた。
「お茶………ね」
このビーカーに入れられた緑茶にも、奏汰はすっかり慣れてしまっていた。
机近くにあった回転式の作業用の黒い椅子に座り、背もたれにもたれかかりながら、お茶を啜った。
友里が来るまでの間、奏汰は周りを眺めた。
左側の壁には先ほど述べた棚以外は置かれていない非常にシンプルなものだった。
右側の壁には灰色の布に覆われた『なにか』が置かれている。
何だか分からないが、つい1年前から突如としてそこにあり、以来堂々と置かれている。
大きさはおよそ建物の2階ぐいらいである。
友里にこれが何か尋ねても、はぐらかすばかりである。作ったものは何でも奏汰に見せる彼女にしては珍しく、それに触れることは危ないからと禁止している。
奏汰も少し気になりはしたが、わきまえるべき事はわきまえているので、不要な詮索はしなかったし、布で中身は見えないものの、至る所に凹凸があり、大きな実験器具か何かだろうとしか考えなかった。
「お待たせ!!」
裾が床にまで届くダボダボな白衣を着た友里は、何やら野球で使うようなプロテクター一式を持ってきた。
「……昨日遅くまで作ったって、まさかそれ?」
「そう!名付けて、絶対安全ちゃん!!」
今に始まったことではないが、友里はネーミングセンスは壊滅的であり、奏汰もそれは熟知しているので、敢えて名前には触れようとはしなかった。
それよりも彼女が作ったものがどんな物であるかについて、注意深く観察した。
白を基調とした胸当て、肘当て、膝当て等々は光沢がなく、光を反射しなかった。
どれもシンプルなデザインで、機能性重視にした造りのようだった。
「なんか、うん、普通だな」
チッチッチと人差し指を振り、ドヤ顔で奏汰の目前に胸当てに差し出した。
「これはね、ゆっくり触ったり折り曲げたりすると柔らかくて曲がりやすいけど、強い衝撃には一瞬で固くなるんだ!」
「ああ、なんかネットで見たことあるな。防弾ベストとかで使われてる技術じゃなかったっけ?」
「そうそう」
「でも、よく分からないけど、なんか素材が違うっぽい?これ、何で出来てるの?」
「企業秘密です」
しーっとでも言うように人差し指を口にあて、ウィンクをしながら友里は言った。
「企業秘密て」
「それで、ここからが凄いの!ちょっと着て、腕のボタン押してみて!」
「え?これ着るの?俺が?」
「はやくはやく!」
そう友里に促されて、仕方なく奏汰はプロテクターを全身に装着した。
なんだか、SF作品に出てくる軍隊が身につけていそうだな、と彼は思った。
見た目に反して着てみると軽く、動きはある程度制限されるものの、歩いたり、物を運んだりするのには何ら問題なさそうだった。
「おおー!すごい似合ってる!」
「そうでござんすか。それで、どれを押したらいいんだ」
プロテクターを付けた姿を見て目に星を宿している友里のテンションをは逆に、奏汰は半分呆れ気味に訊いた。
「えっとね、右腕でも、左腕でもいいんだけど、カバーを開けて、ボタンがあるから押してみて」
促されるまま左手で、右腕につけられたプロテクターのカバーを開き、そこにあるボタンを押してみた。
するとその動作に反応して、右腕のから光が発せられ、空中にモニターらしきスクリーンが展開された。
「うお……!なんだこれ」
「フォログラムってやつだよ」
彼女のこの言葉には、奏汰も驚愕した。
未だかつて、これほどのものを作ったことなど誰もいない。
フォログラムには奏汰の心拍数や、感情などのパラメータが表示されており、その他にも項目がある。
「奏汰の健康情報とか、あとは簡単なレーダー機能もあって、人がいると検知してくれるよ。指を動かしてみて。操作できるから」
右手の指を動かすと、彼女の言った通り操作が出来、黒い画面の中心に青い点が、その横に黄色い点がある。
これは、奏汰と友里の2人の生命反応である。青が奏汰、黄色が友里。
「まじか。これ、すげーな。え、シンプルに凄い。いつも作ってるガラクタじゃない!」
「ちょっと、ガラクタってどういう意味!?」
「ははは、ごめんごめん」
笑ってごまかす奏汰、プクーと口を膨らませる友里。
こんなやり取りはしばしば行われており、2人の平和なひと時である。
「いやでも、本当に凄いよ。俺じゃなくって、誰か他の、同じ科学者にでも見せてやれよ」
自分が成し遂げたことでもないのに、なんだか誇らしげに感じた奏汰は友里に向かって、朗らかに言った。
しかし、友里は首を横に振った。
「ううん、これは誰にも見せない。奏汰だけにしか」
「何で?こんなに凄いのに」
「それは………」
途端に言葉に詰まる友里。さっきまでの元気はどこへいったのか、なんとなく気まずそうにしている。
「まぁ、いいや。これ、返すよ」
プロテクターを脱ぎ、一式を友里に手渡そうとした。
すると友里はそれを拒んだ。
「ごめん、そのプロテクター、そっちに置いてくれないかな?」
「また?」
「うん。ごめんね」
友里は時々、自分で発明したものを奏汰の部屋に置くように頼むことがあった。内容はそこまで大きなものではなく、小物で便利グッズが多かった。しかし、今回はそれなり場所をとる。そのことに違和感を覚えながらも、奏汰は結局受け取る事にした。
「そういえば」と奏汰はプロテクターを持ち運べるよう、箱にしまっている友里に話しかけた。
「今日も親いないんだろ?家で夕飯にしようか。何がいい?」
「パスタがいい。トマトスープもつけて」
「おっけ、じゃあ、持ってきてやるから、ちょっと待ってな」
「うん。待ってる」
奏汰はプロテクターの箱を持って、一回自宅へと戻り夕飯の支度をした。必要な食材を冷蔵庫から取り出し、また友里の家へと戻った。食器や調理器具を並べ、両手を丁寧に、丁寧に洗い、お湯を沸かし、まな板を取り出して食材を切り始めた。
中学生の頃から、両親が仕事で家にいない友里のために、奏汰が夕食を作って持ってきて、一緒に食べるようになったのだ。
グウッと空腹によりお腹がなり、思わずお腹を押さえる友里。
「お腹空いちゃったな。あと、どれくらい一緒にいられるかな。奏汰……」
彼女以外誰もいないラボでそっと呟くも、その声は静寂に溶け込み、通気口から流れてきた冷たい空気が彼女の髪を撫でた。