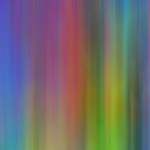白い壁と焦げ茶色の木目調の屋根はくっきりと色と色と分けているお寺のとなりの駐車場では車が数台止まっていた。その中には黒くて前後に長い霊柩車が待機していた。
寺への入り口となる門の上には、漆黒の羽に身を包んだカラスがじっと、お寺の方を見ている。
不気味なその姿に加えて、人気のない木々が風で揺れ、怪しい音を奏でているから、一種のホラー映画のような緊張感と冷たさを与えている。
普段であれば静かで、1週間に何回かは近所の小学生が遊びに来るものだが、しかし、今日に限っては異様に静かだ。いや、単に静かなのではない。なぜなら、静かなそのお寺には人がいるからである。しかも複数人。一見すると奇妙に見えるかもしれないが、寺に集まる人の気配は全て、そのお寺の建物の中に集中していた。
怪談話で出てきそうなほど低い唸り声にもにた調子で、オレンジ色の正装姿のお坊さんがお経を読み、その背に黒い服を着た人々が椅子に座り、ある者は無表情を維持し、またある者は涙を流していた。
奏汰もその1人だった。彼はこの儀式が始まる前からずっと暗い表情をしており、母親や父親と一緒にいても、一言二言程度した話さなかった。
お坊さんや奏汰たち、そして彼女の遺族を含めた人たちの目の前には祭壇があり、その上に白い棺がしんと横になっていた。
そしてその棺を囲うように咲き乱れていたのはお供え物の花である。もちろん、実際に咲いているわけでは無い。しかしながらこれ以上ないほど豪華な花の群は、咲いていると言われても不思議でないほど密集していた。
その花の中央には写真立てがあった。
水色の髪をなびかせ、海辺でこちらに笑顔を向ける少女の顔。
友里である。
奏汰は写真を見られなかった。
これは昔の写真ではない。むしろ最近のものである。高校入学前の春休み、奏汰と友里は志望校に合格した祝いに、家族ぐるみで海へ旅行に連れて行ってもらったのだ。夏でもないのに海に来たのは、友里が運動音痴で泳ぐことが出来ないため、季節が冬であろうが、夏であろうが彼女とって大した問題ではなかったのだ。奏汰としては幼馴染の水着姿が見れず、残念に思ったものだが、それでも彼女と旅行に来れたことに喜びを隠せなかった。
そして訪れた海は太平洋に面しており、岸には鳥居が鎮座しており、毎朝、日が昇るのを迎えて、赤く染まるのである。
この日はちょうど快晴であり、鳥居の中に光を降り注ぐ太陽を見ることができたのだ。
今、お葬式で使われている彼女の遺影はこの旅行で撮られた、奏汰と友里にとって大切な思い出の中の1ページである。
友里………。心の中で呼びかけてみる。返事は、ない。友里…………友里、友里。何度も呼びかける。帰って来るのは誰かも分からないお坊さんのお経を読む声だけである。
それと他に、声がした。
「不審死だったんだって」
「怖いね」
「優しい子だったのに」
「どうでもいいのに」
「勝手にしとけよ」
ヒソヒソとした厭な声。クラスメイトである。
「静かにしなさい」
小声で担任の佐藤先生はお喋りしている生徒たちを制する。今この場には友里の両親、親族、奏汰、奏汰の両親に加えて、学校の校長、教頭、教員一同、クラスメイトが座っている。
友里には友達が少なかっため、クラスメイト以外に同い年の少年少女はいなかった。
クラスメイトは、もちろん半分以上は真剣に葬儀に臨んでおり、その表情も彼女の不幸に心を痛めてのものだった。しかしどこの世界にも心の無い人はいるもので、一部のクラスメイトは彼女の入る棺に向けて冷たく突き放した言葉をつぶやいたり、その死因について噂する者もいた。
奏汰にとって、それが許せなかった。
自分の大好きな人がこんな風に扱われているのだから。
何故、こんなにも心ない言動に平気な人間がいるのだろうと、心の奥底から人そのものに恨みを投じそうになった。
それまで無表情だった彼の顔は、キッと皺が寄り、斜め右後ろに座る、恐らくヒソヒソと話していたであろうクラスメイトを睨んだ。
「奏汰………落ち着け」
横に座る友樹が落ち着き払った声で、諭すように言った。
奏汰が左側をむくと、友樹が喜怒哀楽を読み取れない顔で彼の事を見つめている。
ここでようやく奏汰は落ち着きを取り戻し、前を向いた。
それから、奏汰はひたすら彼女との思い出、彼女に言われたこと、彼女の姿、声、温もりをまるで壊れたレコードのように延々と繰り返して思い出し、しっかりとお別れできるようにと、他の音を気にしないようにただじっと棺を見つめた。
葬式は奏汰にとってあっという間に終わってしまった。
友里の遺体が火葬場に運ばれる前の、棺をみんなで囲んで最期のお別れを伝える時には、奏汰は彼女の顔を見なかった。近づこうともしなかった。代わりにクラスの女子や親戚の人たちが棺のまわりで「さようなら」と涙を流していた。
「良かったのか?最期にお別れを伝えなくて」
全ての儀式が終わったあと、奏汰と友樹は寺の門をくぐり抜けて、塀のそばでようやく話した。
「いいんだ」
奏汰は静かに答えた。
「そうか。まあ、なんだ、その、困った時は力になるから。元気だせよ」
「ありがとう」
友樹はそれだけ伝えてしまうと、奏汰に背を向けて歩き、帰途へとついた。
「奏汰、帰るぞ」
筋肉質の身体を喪服で包んだ男が奏汰の肩を掴んだ。
「うん。父さん」
彼の肩を掴むこの男は奏汰の父であり、土木関係の仕事をしている。そのせいか軸対労働にはこれ以上適任はいないと思えるほどの屈強な男として周囲の目を引いている。
「それじゃあ、私も帰るからね。向こうのご両親にも挨拶できたし、行こっか」
奏汰の母親も、彼が歩き出すのを待ち、優しく微笑みかけた。
奏汰、母、父の3人は歩いて、お寺の前の道を歩き始めた。
歩道の脇に植えられた街路樹は桜の木であり、春であれば淡いピンク色というよりかは白に近い花びらが満開となる。古びてはいるが歴史を感じさせる寺の景観も相まって桜の名所として誰もが訪れる道だ。
奏汰は両手をポケットに突っ込んでゆっくりと歩きながらえ上を空を仰ぐ。
桜の木に花は無い。代わりに生き生きとした葉が、木の枝の一本一本を丁寧に緑色に染め上げており、瑞々しさを感じた。
両親は友里のことについて互いに話しながら歩いていおり、そこから話題が点々と変わっていくが、奏汰はとてもそんな気分になれない。前を歩いてる2人に奏汰はどんどん置いて行かれていった。気が付けば奏汰との距離は数mもあいていた。
両親はちらっと後ろを見て、心ここにあらずといった奏汰の様子に気をかけながら、自分たちにはかけてあげる言葉すら見つからない、というように前を向いた。
家に着くころには日は地平線の少し上ぐらいにまで傾いており、オレンジ色に燃える太陽の姿が分厚い雲にくっきりと浮き出ていた。
自宅に帰ると奏汰は制服を脱がないまま、自室のベッドの中へ倒れこんだ。
いつものこの時間なら、友里の家で研究を手伝わされている頃だが、今日は、いやこれからはもう2度とそんな日常には戻れない。
電気もついていない部屋は、日が完全に沈みきって外の世界に人々を眠りにつかせる闇が訪れてしまうと、街灯の明かりが窓から入り込んだ。そんな時間になっても奏汰はベッドから降りてこない。掛け布団もかけずに、ただ片腕を枕にして、友里を思い出そうとする悲し気な感情と、無気力感だけが彼の心を支配していた。
明日は、学校。もうお風呂に入り、夕食を食べ、課題を終わらせていかないといけない。しかし今は、そのどれもやりたくない。ただこうして横になっていたい。このままベッドの上で溶けて、消えてなくなって、そして友里にまた会いたいと思った。
奏汰は気づいたのだ。友里がいたこと大切さを。かけがえのない日々を。大好きだったからではない。彼女という存在が奏汰を変えた。10数年という長い年月をかけて共に過ごしていた人と突然の別れが、彼の心にすっかり大きな穴をあけてしまった。
下から夕飯に呼ぶ母親の声など、彼の耳には届いていない。
壁に身体を向け、目を閉じる。
目の前に浮かぶ、友里の笑顔。
そして「大好き」という言葉。
彼は、人生で、大きなものを失った。