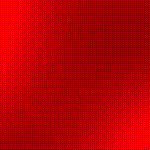25:モンハンに引き継がれるカプコン魂2
さて、モンハンで商売をする(★補1)にしても、まずはゲームそのものを知らねば話にならない。
まあ、実物をやるのが一番早いのだが、ソレと併せて、『カプコン』というメーカーの「らしさ」の系譜を理解しておけばさらに理解は早まると思われる。
実を言うと、日本では、モンハンの様なタイプのゲームはヒットしない、と長年言われてきた。それがどういう事かと言えば……この手の大作ゲームには「ゲーム性」と「ドラマ性」という二本の柱があり、日本国民は、どちらかというと「ドラマ性」重視のゲームを好む傾向が強かったからだ(★補2)。
しかし、『モンハン』は「ゲーム性」重視で「ドラマ性」は乏しい。その代わり、『カプコン』の過去作品に見られた「おもしろさのツボ」が、しっかり系譜として引き継がれており、これが今作のヒット要因の一因であることは疑いようがない。
元々はアーケードゲームメーカーであったカプコンは、その一作目『バルガス』の時点で、すでに「武器の使い分け」による面白さを採り入れている。コレは後に『魔界村』へと進化し、武器のセレクトという概念は、やがてファミコンの『ロックマン』で自在性を獲得。セレクト次第では、苦戦したボスが簡単に倒せたりするようになる(★補3)。
『カプコン』のゲームイメージには、常に「難しい」という側面が際だつが、この難しさの要因はこの状況に合わせたセレクトの戦略性に起因している所が大きい。最初からある基本武器だけで突き進んでいると恐ろしく難しい反面、正解のセレクトさえつかめば案外と楽に進めてしまうのである。
『モンハン』にもこの点は色濃く引き継がれており、武装を変えて出かけるも良し、ストイックに一種で突き進んでも良し、という好バランスが売りの一つとなっているのだ。(以下次号)
★補1
急成長タイトルの宿命か、ユーザー数が多い割に「場」に乏しい側面を持つため、ネットカフェ等でのプレイスペース提供の他、メーカー公式を取り付けてのファンジンイベントや、腕を磨いて出張パートナーをやるなど、アイデア次第では色々出来そうである。
……ただ、時々噂に聞く、改造データの有償売買などは、法的にも制作者の人格権を侵害する可能性もあるため、さすがにいかがな物か。この点にだけは要注意である。
★補2
コンピュータRPGの元祖と言われる『ウルティマ』『ウィザードリー』はどれも欧米の物だが、そもそも欧米にはその時点ですでに「テーブルトークRPG」の文化があり、ゲーム内のキャラクターは自分の分身という意識が強く、イベントが起こると自分が意図しない方向にキャラが動く事が多いドラマ性のあるゲームはあまり好まれなかった。
対して日本ではコンピュータRPGの方が先にメジャーになった事と、これが家庭用ゲーム機の表現力進化の時期と重なった事からドラマチックなイベントを擁するゲームが多産され、ユーザーもコレを好んできた、という流れがある。
★補3
『魔界村』では、武器の変更はアイテムを拾わねばならず、必ずしも効果的な武器が必要なときに手に入るとは限らず、どの順番でアイテムを拾ってドコまで持って行くかを考えることが攻略上の要点になっている。
対して『ロックマン』では、ボスを倒して手に入れた武器はエネルギーさえあればいつでも選択可能であり、アレでもないコレでもないと、仲間内でワイワイ言いながら正解を探っていく、という遊び方が生まれてくる。
コレが後に対戦型ゲームの「人vs人」という概念に繋がるのだが、この辺の詳細はまた次号で。
◆次回は「26:モンハンに引き継がれるカプコン魂3」
■■■■■■■■■■■■□免責事項□■■■■■■■■■■■■
記載内容を利用して生じた結果につい て、当方では責任がとれませんのでご了承ください。
また、筆者が思った事や感じた事を率直に書いている事柄に関しましては、反証可能な事実誤認以外の訂正には応じられません。
URLで紹介した先のページの著作権は、そのページを作成した人にあります。
URLを紹介する事に違法性はありませんが、文章等を転載する場合は、作者の許諾が必要となります。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 執筆者紹介 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
◆星雲御剣(せいうん みつるぎ)
80年代後期ファミコンブームの頃から各ゲーム誌で攻略記事を担当。
ゲームのみならず、マンガやアニメにも造詣が深く、某大手出版社の入社試験では、面接官に聞かれたウルトラマン、仮面ライダー、ガンダムの顔と名前を全部言い当てたのが合格の最大の決め手になった、と言われている(笑)。
独特のオタク感を実生活に反映させる生き様を模索、実践する求道者。
◆清水銀嶺(しみず ぎんれい)
唐沢俊一氏主宰の『文筆業サバイバル塾』第一期塾生。
既刊『メイド喫茶で会いましょう』(共著)
『ためログ』にて記事を執筆。