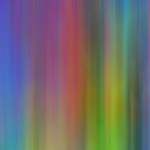街並がゆっくりと流れていく。電線に鳥が何羽も留まっており、細いはずの電線が黒く太い線に見える。大通りには車が行きかっており、そばに備えられた歩道にはカートを押す老人と下校中の小・中・高生以外が歩いている。そんな日常という風が、この街に吹いている。
その街に気配を溶け込ませながら、とぼとぼと奏汰は家への帰途についていた。ただ一つ非日常的なものがあるとすれば、彼のペンダントぐらいだろうか。
健司にからかわれて学校内ではポケットにしまっていたが、授業が終わりホームルームが終わり、校門を抜けるとすぐに奏汰は首から下げたのだ。
そうすれば、いつも一緒に下校していた彼女がそばにいてくれているような気がしたからである。
「あんな奴、言い返せばよかったのに」
ペンダントが青白く点滅し、同時にフライアの声がした。話題に出しているのは、今日の出来事のことだ。
「言い返しても無駄だ。あれは手に負えない」
ため息をつきながら、詰まらなそうに奏汰は返した。
どこかを見ているわけでは無いけれでど、視線は空だか、道に並ぶ家だか、無心に眺めている。
「ふーん………」とフライア。「人間、色々なのがいるものだねぇ……………」
「そういうお前はどうなんだよ?」
「私?」
「お前、ロボットの癖にかなり人間っぽいじゃん。今も、誰か友達に電話してる気分だぞ、こっちは」
周りに人がいないように注意し、人がいるときは小声にしたり言葉を切って、奏汰はフライアと会話をしている。
「それは、私はこの世界の技術では到底作れないぐらいの高性能AIだから」
そう言うフライアの声は自身に満ち溢れていた。
彼女に人間の身体があれば、鼻を高くし、胸を張り、ポンッと片手を胸につけて自慢げに振舞っていたことだろう。
「自分で高性能って言っちゃうのか」
「事実なんだから仕方ないよ」
謙遜も遠慮もなく、フライアは応える。こういう、謙遜とか遠慮という概念自体を持たないのは人工知能らしいと言えば人工知能らしいのだろうか。そんな風に考えている奏汰だったが、やがて彼女と話すことに少し疲労感を感じてきた。
彼にとって、彼女の存在は今までない、それどころか世界中どこを探してもないと思えるほどの代物なのだ。
もうすぐ家に着きそうというところで、ふと、見覚えのある影が地面に在るのに気がついた。
「ん?あれは」
中学校の制服を着た小柄なショートカットの女の子が、道の端にしゃがみ込んでいる。
その雰囲気には覚えがある。
「霞ちゃん?」
その女の子は奏汰の声に反応し、バッと後ろを振り向いた………。
「あ………お兄さん……………」
いつもならどこか嬉しそうな声色で、子犬のように奏汰に話しかけてくる彼女であるが、この時だけは何故かどこか気まずそうな顔をして、目を反らしてしまった。
しゃがんでいるせいで、制服のスカートの裾が地面についてしまって、土色に汚れている。
中学生である彼女は今、下校中であるはずだが、何故、こんなところで地面にしゃがんでいるのだろうか。
奏汰は疑問に思って、たまらず、どうしたの?と訊いてみた。
霞は立ち上がり、奏汰の方に向き直った。
少し手をモジモジとさせながら、なにやら気まずそうに、言いづらそうにしつつも、じっと返答を待つ奏汰の視線に耐えかねて、ついに答えた。
「えと、あの、実は………落としてしまって……………」
「落とし物…………?」
「いつもつけてるやつ……」
そう言って、霞は例の黒い学生鞄を奏汰に見せた。
「あ」
奏汰にもようやく、何を落としてしまったのか分かった。それは、霞がいつも鞄に付けているクマのアクセサリーであった。いつもなら鞄の端のほうに付けてあったはずなのに、今はそこには無い。
「紐が、もう古くなってたみたいで、どっかに落しちゃったのかなって……………」
悲しそうな声な霞。その姿がまるで主人に叱られた子犬のようで、もしも彼女に犬の耳があれば、頭にぴったりと垂れ下がっているだろう。彼女にとってそれほどまでに、大切なアクセサリーだったのだろうか。きっと、大切なのだろう。
あまりにも悲しそうな表情をして、哀愁を漂わせるものだから、奏汰は気の毒に思って、そして彼女と同じように地面にしゃがみ込んだ。
「じゃあ、俺も探すよ」
「………え?」
気の抜けた声を漏らし、霞は奏汰の顔を見た。
触ればモチモチと柔らかそうな可愛らしい頬は、すっかりあっけに取られて力が緩んでいる。
対して奏汰の表情は優しそうで、夕陽のおかげで眩しく見えた。
じっと彼の顔をまじまじと見ていた霞はハッとして、忙しく首をブンブンと横に振った。
「大丈夫です!私1人で探しますから!」
「そんなこと言わずにさ。2人で探した方が早いよ」
「でも……」
「いいから。いいから」
そう言って、奏汰は視線を落とし、アスファルトに生えた雑草と雑草をかき分けたり、側溝の中を覗いてみたりと彼女の大切なものを探し始めた。
その後ろで霞はオロオロとしているばかりだった。
「本当に、大丈夫ですよ……………。お兄さんに迷惑なんてかけられないですよ」
そう訴えてみても、奏汰に止めえる気配はない。それどころか、場所を変えてまた雑草と雑草の間を探している。
「お兄さん………」
「霞ちゃんの大切なものなんだろ?だったら、絶対見つけなきゃな」
この言葉は、彼女に向けているのは勿論だが、自分に重ねてもいた。
「……………」
彼女は答えなかった。
ただ、彼女にとって大きな奏汰の背中を見つめ、自分のうっかりのミスに奏汰を巻き込んだことに自責の念にかられている。しかし、このまま彼の厚意を無下に断るわけにも、このまま黙って立っているわけにもいかない。
ようやく決心して、霞は奏汰のそばに近寄り「下校する前にはあったので、多分この辺のどこかに落ちているんだと思うんです」と控え気味に伝えた。
「ってことはここから学校までの間に落したんだよね。じゃあすぐ見つかるよ、ちょっと待ってて」
いつもとは違う、他人に気を使った口調で、奏汰は応えた。声のトーンは普段とさほど変わらないが、今、知り合いの女の子を助けている彼の姿は間違いなくかっこよく見えることだろう。
私も探さなきゃ!と霞も奏汰と少し離れたところで地面にしゃがみ込んだ。
ときどき通行人が、地面にしゃがみ込む男女2人を訝しげに見つつも、特に話しかけるわけでもなく、何事もなかったかのように通り過ぎて行った。
信号機の光が徐々に明るく感じられるほどに、日が沈んでいく。これは奏汰にとっては誤算だった。この場所から中学校までそんなに遠くない。2人で探せばあっという間に見つかるだろうと思ったのだ。しかし、現実はそうはいかない。時間がゆっくりと、でも確実に過ぎていくのを、はっきりと感じた。影が伸び始めているのだ。
おまけに辺りも薄暗くなって来ている。
ずっと下を向いていて、そろそろ体勢がきつくなってきた奏汰は腰を反った。
「あの、お兄さん。もう、いいんです。諦めることにします。その、ありがとうございました」
胸元のところで左手を右手で握りながら、霞は言った。
夕陽のせいもあってか、彼女の顔に浮かぶ影は哀愁を漂わせるものだった。目元はなんだか涙を堪えているようにも見えた。
それには奏汰も気がつき、朗らかな声で返す。
「いやいいよ。俺、この後予定ないし」
「いえ、本当に」
「でも」
「いいですから!お兄さんは!早く帰ってください!」
痺れを切らしたのか、霞は声を若干荒げながら、奏汰の背後にまわり背中に背負ったリュックを押して帰るように促した。
「ちょちょちょ」
バランスを崩しかけながら奏汰は一歩、一歩と前に足を出す。
自身が持つ全体重を以て霞は奏汰を押す。もちろん彼に対して本気で怒っているわけでも、彼を嫌っているというわけではないようだった。その行動は、どうやら、ただ単に申し訳なさからきているようであった。
奏汰の方も女の子相手に全力で踏ん張って無理に立ち止まろうとはせず、霞に押されるがままにされている。
「分かった!分かったから押すなって」
顔を横に向け、霞に止めるように言った。
その時だった。一瞬だけ、視界の端に、キラッ何かが光った気がした。
奏汰はすぐに目を凝らしてその場所を確認した。キラッとした光があったのは、家と家の狭い間の地面。雑草やら野花やらが無秩序に生えているところに何かがある。太陽の光を反射する何かが。ただし、かなり奥の方にあるようではっきりとはしない。
「ちょっと待って霞ちゃん!」
先程よりも大きな声を上げた。何かが奏汰に言いたそうにしていることを汲み取り、ようやく霞は彼を押す力を緩めた。
彼女の物理的な圧がなくなったことで、自由を取り戻し、奏汰は道端へと歩み寄った。
膝を地面につけて、光ったものがあった場所をじっと見ているが、元々薄暗いところな上に日も沈みかけているので人間の肉眼では見づらかった。
「どうしたんですか、お兄さん」
「いや、ここに何かあるんだけど……………。暗くて見えないな」
そう彼が零すと突如として、彼の胸元のペンダントが輝きだした。
光は青白く、でも今までより一層明るく光った。
「え、な、なに!?」
目の前で起こる奇妙な現象に、霞は驚いてきょとんとしている。
身に着けている本人である奏汰も、一瞬ペンダントを隠そうと両手で覆いかぶせたが、指と指の隙間から光が漏れていた。そしてすぐに、その光があれば目の前の細い暗闇を照らすことが出来ると考えるようになり、指でつまんで、前へ出してみた。
ペンダントの光によって、見えなかったところが見えるようになり、見覚えのあるそれが確かにそこにあった。
「お、見つけた」
思わず声をだして、奏汰は家と家の隙間に手を伸ばした。
ひんやりとした薄い小さな板のようなモノを掴み、取り出した。
それは霞が普段鞄に付けている、白いクマの絵が描かれたアクリル板のアクセサリであった。
土がついて少々汚れてしまっているが、目立った傷はない。
「ほら、これだろ」と奏汰は付着した土を指で拭って、掌に載せたそれを目の前の可愛らしい少女に差し出した。
この時、彼女はアクセサリーを貰った時の事を思い出した。彼女の目の前に立つ奏汰はきっともう忘れてしまっているだろうが、霞は覚えている。というのも、霞が大切にしているというクマのアクセサリーは、かつて奏汰が彼女にあげたものだったのだ。今、そのアクセサリーをプレゼントしてくれた奏汰と、見つけたアクセサリーを手渡した奏汰の姿が重なって見えた。
「わぁ!これ!これです!」
ホッと安堵したように、すぐにアクセサリーを手に取る霞。今度はお気に入りのおもちゃを手に入れた猫のように、彼女のまわりに甘い雰囲気が漂っていた。
すっかり気分をよくした霞に奏汰も内心安堵していた。
「ありがとうございます。お兄さん」
霞はニコッと可愛らしく笑った。その笑顔に奏汰は癒されつつも、きっと、学校ではこの笑顔に何人もの男子たちがメロメロになっていることだろう、と普段の彼女の学校生活を想像した。
「ところで、そのペンダントはどうしたんですか?さっき光って……………」
両手でアクセサリーを持ちながら、霞の視線は彼のペンダントに移っていた。
「あ、えと、これは、その」と奏汰はふいを突かれ、言葉を探した。何と言うべきか迷ったが、結局事実の一部を話すことにした。
「これは、友里から貰ったものだ。あいつ、変なモノ作る癖があっただろ?そのうちの一つだよ。光るペンダント」
可笑しいだろ?と笑って見せた奏汰だったが、そのその眼は彼女を失った寂しさにわずかに震えていたし、霞もそれを読み取っていた。
「…………小黒先輩の事、聞きました」
「そうか………」
沈黙が流れる。2人の間には、ただ、夕暮れの涼し気な風が吹き抜ける。
電柱に備え付けられた街灯が順番に付いていく。
沈黙を破ったのは、奏汰の方だった。
「そろそろ、帰ろうぜ」
「………そうですね」
今度は落とさないようにと、霞は鞄に入れてあった筆箱に大切にしまいこみ、そして奏汰の横を、小さな歩幅で歩き始めた。アクセサリーを見つけた時よりはテンションは落ち着いてきており、少し俯き気味になりはしている彼女だが、しかし、今この時を噛み締めるが如く、身体中の感覚を研ぎ澄ませている。
2人は歩く。家の塀の上を猫が歩く。横を車が通る。
車道側を歩くのは奏汰。そんな彼に守られるように歩くのが霞。
カラスは黒い翼を音を立てずに、でも力を込めて飛び、夕焼け空に溶け込んだ。
また、沈黙が流れる。黄昏時。輪郭がぼやけ、人ならざるものと出逢うとされる時間。奏汰もまた、彼の想いの中に、今はもう居ない友里のことを思い出していた。唐突に言葉に表すことのない寂しさに、彼の心は蝕まれた。
やがて、彼の家に着いた。
「それじゃあ、ここで。気を付けて帰ってくれよ」
玄関に身体を向けながら、奏汰は手を霞に振った。
「もう、失くすなよ」と冗談交じりに笑ってみせながら。
しかし、霞は真剣な表情で奏汰を見つめ、ちらっと壁にブルーシートがかけられた友里の家の方に視線を送ると、小走りで奏汰のもとに寄った。
「悩みがあったら、いつでも言ってくださいね」そう早口で伝えると、霞はまた小走りで自分の家へと向かっていってしまった。
奏汰は、いつもなら「自分の方が年上なのにな」と内心ツッコむものだが、今日だけは去り際の霞が大人びて見えた。